『異邦人』について
今週のお題「本棚の中身」

現在、web小説サイト「カクヨム」での活動が中心になっていて、あまり、こちらのブログにこれないのですが、お久しぶりです。
みなさま、お元気でしたか?
さて、カクヨムで小説を書いていると、たまに、リクエストがあるんです。最近では、カミュについて論説を書いてって。
いや、論説って、アメだよ。タヌキだよ。無理さって思っていたとき、たまたま、子どもの本棚にカミュ作「異邦人」がありました。
んで、数十年ぶるに読んでみてカクヨムに書いたものなんですが、ブログでもいいかもって再掲しました。
お読みくださると嬉しいです。
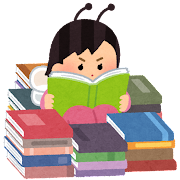
カミュ作『異邦人』について
「今日、ママンが死んだ。」
印象的な、この一行ではじまるカミュ著『異邦人』は、その後も主人公ムルソーの一人語りで進んでいく作品です。
冒頭数ぺージで、かつて20世紀初頭に一世を風靡した実験的小説の手法『意識の流れ』が、効果的に使われた作品だと私は思っています。
まず、『意識の流れ』ですが、これは米国心理学者ウィリアム・ジェイムズが論じた心理学の概念で、「人間の意識は静的な部分の配列によって成り立つものではなく、動的なイメージや観念が流れるように連なったものである」(ウィッキペディアより引用)としたものです。
20世紀初頭の作家たちが、この心理学的概念を文学として実験的に使った手法が『意識の流れ』です。登場人物の内的思考を筋を通して書くのではなく、乱暴に書けば、絶え間ない流れとしてダダ漏れさせる方法です。
いわゆる、
「人間の精神の中に絶え間なく移ろっていく主観的な思考や感覚を、特に注釈を付けることなく記述していく文学上の手法」という表現のひとつです。
1920年代にはじまった、この手法で書かれた作品群。
ジェイムス・ジョイス「ユリシーズ」(1920年)
ヴァージニア・ウルフ「灯台へ」(1927年)
などが、いわゆる『意識の流れ』の代表作と言われています。
作品中での独白は論理的ではなく、知覚、印象、感情、記憶、連想、知的思考など、意識の働きの全てをそのままに描くリアリズム的な小説です。
カミュが、この処女作を発表した1940年には、数々の名作がすでに世に出ていました。彼の作風に影響を与えたと私は思っています。
まあ、『異邦人』を厳密に、その流れとするかは議論の分かれるところでしょうが。
さて、『異邦人』の冒頭からはじまる、主人公の独白。同系列にならぶ事象。私たちは、主人公ムルソーが思考する洪水にさらされます。
母の葬儀で養老院に到着したこと、
夏の太陽が暑いこと、
院長が長い意味のない説明をすること、
エトセトラ、エトセトラ……。
私たちは、ムルソーの見たもの、そのままを知ります。ムルソーがどう養老院まで行って、そこで誰と出会い、どんな天気で、何が見え、どうしたかを彼の日記を読むように追っていきます。独白にも関わらず客観的に事細かに知るのです。
読点「、」と接続詞「それから、それに」などの多用によって、まるで、その場にいるかのような臨場感で引き込まれます。
その淡白な描写。その印象は、いかにも乾いています。
そこには、過去も未来もなく、ひたすらに、《今》しかない。
《わたし》の内面を書く近代日本の特有文学『私小説』と似ていますが、あきらかな違いを感じるのは、この今に対する、ある種、残酷とも言える丁重極まりない描写と乾きです。
もう一つ、この作品で秀逸なのは、作品全体を通じて醸し出しす、主人公の狂気に近い純粋さかもしれません。ある種、神の思考に近いのです。
にも関わらず、自分はムルソーだと共感できる人は少ないでしょう。
『異邦人』は不条理の小説とよく言われてきました。
それは、主人公ムルソーが、母親の葬儀の翌日に海水浴に行き、女と遊び、映画を見て笑い、挙句に自分とは関係のないアラビア人を殺害して、その殺害動機について「太陽のせい」と裁判所で証言するからです。
ムルソー以外、ここに書かれる人びとは、非常に『普通の人びと』です。
裁判所の判事も、弁護士も、検事も、神父も、情婦も、養護施設の院長も、チンピラも、友人も、彼らの職業的に典型的な人物ばかりです。これら普通の人びとは、それぞれの職業を、私たちが理解できるように体現しているのです。
この作品で、唯一、理解できない人がムルソーであり、また、実に理解できる人間でもあるのです。それは、人の深い本質をついているからです。
ムルソーは純粋です。彼は嘘を言えない。彼は殺害動機を「太陽のせい」と説明します。
彼にとって殺人は、裁判所の判事に伝えたように、
「レエモン、浜、海水浴、争い、また浜辺、小さな泉、太陽、そして、ピストルを5発撃ち込んだこと」がすべてなのです。
人は、生き物のなかで、もっともよく嘘をつく動物です。時に、自分さえも騙して自分自身に嘘をつきながら生きていると、よく思います。
主人公は母の葬儀で涙を流さなかったがために、社会的にも死刑を宣告されてしまいます。
涙を流すという芝居をしないことで、社会から抹殺されるのです。
『社会で暮らす人間が、この嘘をつけない場合、異邦人になってしまう』と、カミュは自著で書いていました。
優れた文学というものは、人の暗部を抉りだし、表に曝け出します。
「異邦人」はそういう作品なんだと思います。
文中、ラストシーン近く、ムルソーは語ります。
「私はかつて正しかったし、今も正しいのだ。いつも、私は正しいのだ。私はこのように生きたが、また別の生き方もできただろう」
彼の不器用な生き方。その不条理さ。私たちは、この作品を読み、裁判官や神父側につきながら、彼ら同様に、とまどいを覚え、次に、彼の嘘をつけないがための、その生き方に嫌悪する『普通』の自分がいます。
そして、彼に共感を覚える、『特殊』な自分もいるのです。
文学とは、こういう毒を持っています。だからこそ、『異邦人』は、いつまでも歴史に残る魅力的な作品なのでしょう。
0と1で構成され、善と悪しか識別しないAIには書けない作品なのです。
この作品が書かれた1940年。フランスがドイツに占領された時代で、当事者にとって、まさに不条理な出来事でありました。カミュの感じた乾いた感情が、作品に反映したとも思っています。
**************
お読みくださって、本当にありがとうございます。